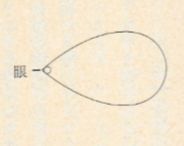�q���[�����A�y��M�v�E�����Îl�Y��w�l���_�x�i�������_�Ёj�Ɍf�ڂ���Ă���A
��m���������u�����ƌ��ʂƎ��R�Ɓv�i1�`24�y�[�W�j���͂̑����E�E�E
�����펯�I�����̂悤�ɁA���R�ӎu�͈��ʓI�K�R�������藧���Ă��Ȃ��Ƃ��ɐ��藧�̂��Ƃ���Ȃ�A���R�ӎu�Ƃ����̂́A���ꂪ�Y�ݏo���s�ׂƕK�R�I�ɂł͂Ȃ����R�I�ɂ������т��Ă��Ȃ����ƂɂȂ�B�Ƃ������Ƃ́A���Ƃ��ΉE���˂��o�����ƈӎu���璼��������̂ł͂Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�B���Ƃ���A�������ĐӔC�Ȃǖ₦�Ȃ��̂ł͂Ȃ����B�ł���Ȃ�A�ނ���A�u�������̎����v�Ƃ��āu���R�ӎu�v�����藧���u�ӔC�v��₦�邽�߂ɂ́A�ӎu���邢�͂��̔w�i���Ȃ��s�҂̐��i��C���ƁA�s�ׂƂ̊Ԃ́A���ʓI�K�R���ɂ���Č��т����Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł͂Ȃ����B���̂悤�Ɍ��т����Ă��Ă͂��߂āA���R�ӎu�̌��ʂł���Ƃ����A�����ĐӔC�T�O���@�\����̂ł͂Ȃ����B�q���[���͂��������B�u�l�Ԃ̍s�ׂɌ����ƌ��ʂ̕K�R�I�������Ȃ���A���`�⓹���I�����ƓK������悤�ɔ����Ȃ���̂��s�\�ł���v�i�{���ꎵ�ܕŁj�B���������q���[���̎��R�_�́A���R�ƕK�R�A���邢�͎��R�ƌ���_����������Ƃ����l�����Ȃ̂ŁA�u������`�v�ƌĂ�A����̎��R�ӎu�_�ɐr��Ȃ�e����^�������Ă���B�i��m�����A21�`22�y�[�W�j
�E�E�E�v����ɁA
(A) �ӎu�ƍs�ׂƂ̈��ʊW�ˎ��R�ӎu�E�s�ׂ̐ӔC�i�q���[���̏ꍇ�B�u������`�v�j
(B) �ӎu���̂��̂����ʊW�Ɏx�z����Ă��Ȃ��ꍇ�ˎ��R�ӎu�i�悭��������ʘ_�Ǝ��R�ӎu�Ƃ̊W�j
�E�E�E�Ƃ������Ƃł͂Ȃ��낤���B�����āA���R�ӎu�ɂ��Ę_����ہA�܂��́u�ӎu�v�Ƃ͉����u���R�v�Ƃ͉����A����ɂ͈��ʊW�̕K�R���Ƃ͉����A�Ƃ������Ƃɂ��ĉ��߂Č����Ă����K�v������B
�ŏ��Ɍ��_���q�ׂĂ������E�E�E�i�P�j�ӎu�ˍs�ׂƂ����g�g�݂��̂��̂��o���̎����Ƃ��Č���Ă��Ȃ��i�Q�j�ӎu�ƍs�ׂƂ̈��ʊW�͂��������������Ȃ��i�R�j�K�R���̊l���ł��Ȃ����ʊW�c���́u�R�v�Ȃ̂ł͂Ȃ�
�܂�q���[���́u������`�v�͂��̑O���肪����A�����������������Ȃ��A�Ƃ������ƂȂ̂ł���B
�ȉ��A��̓I�ɐ������Ă݂悤�i�Ō�Ɏ��R�ɂ��Ă̍l�@��t�������Ă���j�B
�i�P�j���������u�ӎu�v�Ƃ͉����A�u�ӎu�v�Ƃ������̂Ȃǎ��ۂɂ���̂��F�u�ӎu�ˍs�ׁv�Ƃ����g�g�݂͗L���Ȃ̂�
�܂��́u�ӎu�v�Ƃ͉����A�Ƃ������ɂ��čl���Ă݂�K�v������B���̏ꍇ���A���R�u�o���v�ɑ����Č����Ă����K�v������B
���̐l�Ԃ̊w���̂ɑ��ė^������B��̂������肵����b�́A�o���Ɗώ@�Ƃɂ�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�i�q���[�����A�y��M�v�E�����Îl�Y��w�l���_�x�������_�ЁA9�y�[�W�j
�E�E�E�����������u�ӎu�v�Ƃ����o���Ƃ͉��Ȃ̂��A�������猟���Ă����K�v������̂��B�������́u�ӎu�v�Ƃ������̂����ۂɌo���Ȃǂ��Ă��邾�낤���H
���_���猾���Ă��܂��A�u�ӎu�v�Ƃ������̂͒P�Ȃ��t���̊T�O�ł���B����܂ł̌o�܁i�o���j�����ӏ����A����̂���܂ł̍s�ׂ��A������ł���C���[�W��犴�������A�����������o���I��������u�ӎu�v���邢�́u�~�]�v�u���@�v�Ƃ������̂�����I�Ɂh���߁h����Ă���̂ł���B
�u�ӎu���̂��́v���u�o���v�Ƃ��Č���ė��Ă��邾�낤���H �u�~�]���̂��́v�u���@���̂��́v�Ƃ����o�����A�ǂ̂悤�Ɂu�ώ@�v����Ă���ł��낤���H
���ǂ̂Ƃ���A���̂悤�Ȃ��̂Ȃǂǂ��ɂ��Ȃ��̂��B���ۂ̋�̓I�o���Ƃ��ẮA����܂łɌ��Ă������́A�����Ă������́A�����Ă�������̊����o�A����̍s�ׁi�����j���A������������̓I�o���A���邢�͑z�N���ꂽ�o���Ƃ��ẴC���[�W�ł����Ȃ��̂ł���B�����l�X�Ȏ����W�����߂�����ŁA�u�`�������v�Ƃ����u�ӎu�v�u�~�]�v�u���@�v�̉��߂�����I�ɂȂ���Ă���̂ł���B�������������߂ɂ��T�O���i�����S���H�ׂ����A�Ƃ���ƂɂȂ肽���Ƃ��j�ɂ�鎖��I���߂ɑ���a�����������芴���Ȃ�������A������������I���o�ɂ��m�M�������炳�ꂽ��čl���Ȃ��ꂽ�肵�Ă���̂ł���B
�������A�u�����S���H�ׂ����v�Ƃ��u��ƂɂȂ肽���v�Ǝ��ۂɕ��͂Ƃ��ď�������A��̓I�Ɏv�����肵���̂ł���A����͋�̓I�o���ł���B����������͂����܂Łu���t�v�̌o���ł����āA�ł͎��ۂɂ��̌��t�ɑΉ�����u�ӎu���̂��́v���u�o���v�Ƃ��Č����邱�Ƃ��ł���̂��H�ƌ�����A��͂茩���邱�ƂȂǂł��Ȃ��A���ۂɃC���[�W�ł���̂́A���炪�����S��H�ׂ����ƂɂȂ����肷��C���[�W���A�����S�̖����G�̃C���[�W���A����ɔ�����I���o�A������������̓I�o���Ƃ��Ď��������Ȃ��̂ł���B
�܂�A
�ӎu�ˍs�ׁA�Ƃ����g�g�݂��̂��̂ɖ�肪����̂��B�����ł͂Ȃ��A
�o���ˈӎu�i�Ƃ��Ẳ��߁j�Ȃ̂ł���B
�����Ď��ۂɁu�ӎu�v�Ƃ������̂Ɋ�Â��čs�����Ă���̂��A�����͉^�I�ł���B��t���̉��߂Łu���@�v���u�ӎu�v��炪�������̂��A�Ɓh�������h���邱�Ƃ͂�����ł��ł���B�������{���ɂ��̉��߂��u�������v�̂��A�{���ɂ��̂悤�ȁu�ӎu�v�Ƃ������̂��������̂��A�^�킵���̂ł���B
�܂�A�ǂ��ɂ�������Ȃ����̂��u���R�v���Ƃ������łȂ��Ƃ��A�������������ɂ��Ĕ��f���邱�Ƃ��ł��悤���H
�����̂��Ƃ�O���ɒu������ŁA�ȉ��̈�m�����̕��͂����Ă݂�B
�@���R�ӎu�ɂ��ẮA����ł́A�u�]�_�o�ϗ��v�ƌĂ��̈�ȂǂŁA���R�Ȋw�̐��ʂƂ̑ΏƂ̂��ƁA�^���Ȍ������s���Ă���B���Ƃ��A�x���W���~���E���x�b�g�̎����͗L���ł���B���x�b�g�́A�s�ׂւ̈ӎu�����o����ȑO�ɁA�]�̒��Ɂu�����d�ʁv�Ƃ����s�ׂɑΉ������Ԃ���s�I�ɐ����Ă��邱�Ƃ������I�Ɍ��o���A���R�ӎu�̖��͂��������]���ۂ��˒��ɓ���Ę_���Ȃ���Ȃ�Ȃ��A�Ǝ��������̂ł������B����ł��A���������c�_�Ƀq���[���R���́u������`�v�̘_�_���Ԃ�����ǂ��Ȃ邩�B�E�E�E�i�����j�E�E�E���Ȃ��Ƃ��A�u�����d�ʁv�̑��݂ɂ���āA�����Ɂu���R�ӎu�v�̐g�����낤���Ȃ�Ƃ͂����Ȃ����ƂɂȂ낤�B�i��m�����A22�y�[�W�j
�E�E�E���̎����ɂ��āA
�@ �u�s�ׂւ̈ӎu�����o�v�Ƃ͋�̓I�ɂǂ��������Ƃł��낤���H �u�`�������v�Ƌ�̓I�Ɏv�����菑�����肵�����Ƃł��낤���H �����łȂ���A�����ɂ��āu���o�����v�ƌ������Ƃ��ł���̂ł��낤���H
�A ���������u�ӎu�v�Ƃ������̂���t���̊T�O�ł���B�܂肻����������t���́u���߁v�ɐ�Ĕ]�̒��ɏ�I�Ȋ��o���A���̑��A��L�̕��͂ɂ�����u�����d�ʁv�Ƃ������̂�����ė��Ă��邱�Ƃ́A�������R�Ȃ��Ƃł��낤�B
��m�����́A��L�̎����̉��߂�����O�ɁA�܂��́u�ӎu�v�Ƃ͉����������������Ɍ����Ă����K�v������Ƃ������Ƃ��B
�����A������ɂ���A��I���o�A���̑��̗l�X�ȑ̊����o�Ȃǂ̌o���́A������������ė�����́A���ꂪ���ꂪ�K�R�ł��낤�Ƃǂ��ł��낤�Ƃ�����������ė�����́A�����Ɂu���R�v�Ƃ����T�O�Ă͂߂邱�Ǝ��̂��ԈႢ�Ȃ̂ł͂Ȃ��낤���H
�i�Q�j���ʊW�����ۂƎ��ہA�o���ƌo���Ƃ̊W�ł���Ƃ���A�u�ӎu�v�Ɓu�s�ׁv�̈��ʊW�͐������Ȃ�
���̂��Ƃ́A�ْ�
�~�]�ƈ��ʊW �`�w�V�X�e���ɂƂ��ĈӐ}�Ƃ͉����x�̕��͂𒆐S�Ɂ`
http://miya.aki.gs/miya/miya_report5.pdf
�E�E�E�ŏڍׂɏq�ׂĂ���B�u�ӎu�v�Ɓu�s�ׁv�̈��ʊW�͐������Ȃ��̂ł���B�ꕔ���p���Ă݂�B
�������͎��ۂɉ���̌����A����̌����Ă��Ȃ��̂��E�E�E�~�]���̂��́A�{�̂̂悤�Ȃ��̂��������͑̌����Ă��Ȃ��B�h�Ӑ}�h�Ƃ́A�����܂Œ��ۓI�Ȍ��t�� ����A�������̋�̓I�ȑ̌��ł͂Ȃ��B����ł͎��ۂɑ̌����Ă���̂͂ǂ�Ȃ��Ƃł��낤���H
�E�u�����������v�Ǝv�����肵��ׂ����肵������
�E������������肵������
�E�v�����蒝������A������������肵����ŁA�s�ׂ���O�ɗl�X�ȑz���������� �v��𗧂Ă��肷�邱��
�܂�A���ʊW���l����̂ł���A�h�Ӑ}�ƍs�ׁh�ł͂Ȃ��A�������ۂɑ̌�������̓I�o����s�ׂ̊W���l���Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł͂Ȃ��낤���B�����āA���ۂɑO�̓��ɍl�����A���邢�̓��������A�����Ď��̓��ɍs�ׂ����A���̓�̎��ۂ̊Ԃɂǂ�ȋ�̓I�ȁh�W�h������̂��ǂ����A�������J�j�Y���ł�����̂��A����͈��ʊW��F�߂����_�ɂ����Ă͎������̒��ڌo���ɂ͌���Ă��Ȃ��B�܂�h��h�ł���B���ǂ́A�i�s�҂��邢�͍s�ׂ̊ώ@�҂��j�̌��i�o�����A���ہA���ہj�Ƒ̌��Ƃ̊W��F�߂��A�Ƃ������������邾���Ȃ̂��B�i�{���A15�`16�y�[�W�j
���ǂ�
�E����ׂ�����A���������肷�邱�ƂƔ]�̋L���̊W
�E���炩�̈Ӑ}�m�ɊT�O�������Ƃ��̔]�̓����ƁA���ۂ̍s�ׂƂ̊W�A�Ȃ��i�{���A16�y�[�W�j
�E�E�E�Ƃ������悤�ȋ�̓I�o���̎���������ʊW���������K�v������̂��B�����̂��Ƃ��l��������ŁA���ʊW���\�z���Ă݂��Ƃ���ŁA��͂肻���͎��R�ӎu�Ƃ͊W�Ȃ������ɂȂ��Ă��܂��B
���Ɂu�����S��H�ׂ����v�Ƌ�̓I�Ɏv������ŁA�ڂ̑O�̃����S����Ɏ��H�ׂ邱�Ƃ��ł����Ƃ���B����́u���R�ӎu�v�̖��Ƃ������A�P�Ɂu���߂��ꂽ�ӎu�v�ƍs�ׂƂ���肭�q�������A�Ƃ����S�g�̓����̖��ł���ɂ����Ȃ��̂ł͂Ȃ����B
�ʂ̗�������Ă݂悤�B�p�\�R����Delete�̃L�[�����������i���������I���߂ł͂��邪�j�Ƃ��ɁA����BackSpace�̃L�[�������Ă��܂��āA���ꂪ�ȂɂȂ��Ă��܂����E�E�E�Ƃ����ꍇ�ɂ����āADelete�̃L�[���������Ƃ����BackSpace�́A�L�[�������Ă��܂��A�Ƃ����W����ԓI�ɐ�����A�܂�q���[���̌������ʐ��̕K�R���Ƃ������̂����o���Ă��܂��̂ł���B�ʂ����Ă��ꂪ�u���R�v�Ƃ����̂ł��낤���H�i�����u�ӔC�v��₤���ǂ����̊�̈�ɂ͂Ȃ肻�������j
�܂��A��m�����́A
�u�������̎����v�Ƃ��āu���R�ӎu�v�����藧���u�ӔC�v��₦�邽�߂ɂ́A�ӎu���邢�͂��̔w�i���Ȃ��s�҂̐��i��C���ƁA�s�ׂƂ̊Ԃ́A���ʓI�K�R���ɂ���Č��т����Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł͂Ȃ����B�i��m�����A21�y�[�W�j
�E�E�E�Əq�ׂ��Ă���̂ŁA�u�ӎu�v�����łȂ��u���i�v��u�C���v�Ƃ������̂��l���ɓ�����Ă���B�������A�u���i�v��u�C���v�Ƃ������̂��A��͂��̓I�o���̏W�ςɂ���ĉ��߂������̂ł���B���邢�͍s���ɂ����Č���Ă�����́u�X���v�̂悤�Ȃ��̂ł����āA���ꂪ�u���R�ӎu�v�Ƃ͊W�Ȃ��T�O�ł��邱�Ƃ͖����ł���B����ɗ^����Ă�����̂ł��邩�炱���C���Ȃ̂ł���B
�����������o���Ƃ������̂́A������������ė�����̂ł���B��������ė�����̂ɑ��A���ꂪ�u���R�v���Ƃ������łȂ��Ƃ��A�����ɂ��ċ�ʂ���̂ł��낤���H
�i�R�j�K�R���̊l���ł��Ȃ����ʊW�c���͊ԈႢ�Ȃ̂��H
���ʊW�̕K�R���́A���̌J��Ԃ��A�K�����ɂ������炳���Ƃ������Ƃł������B�ł͂��̕K�R�����F�߂��Ȃ��ꍇ�A���ʊW�����݂��Ȃ��ƌ������̂ł��낤���H
���ʊW�ɕK�R��������ꂽ�Ƃ��Ă��A����͌����āu��ΓI�^���v�Ȃǂł͂Ȃ��A�����܂ł���܂ł̌o���ɂ����ď�ɂ����ł������A���邢�͂��Ȃ荂���m���ł����ł������A�Ƃ��������Ɏx�����Ă���ɂ����Ȃ��̂ł���B
����A�J��Ԃ����F�߂��Ȃ��悤�ȁA���̏ꍇ�i���̌o���Ɠ��ꐫ��F�߂��Ȃ��悤�ȏꍇ�j�͂ǂ��ł��낤���H ���̈��ʊW�́u�R�v�Ȃ̂ł��낤���H �E�E�E�����ł͂Ȃ��B����͒P�ɉ����I�Ȑ��_���邢���͊m�M�ł���Ƃ������ƂȂ̂ł����āA���ꂪ�u�R�v�ł���Ƃ����ۏ͂Ȃ��̂ł���B
���Ƃ��A�`����̌��������Ƃ�������a����������Ă��܂����A�Ƃ����悤�ȏo�����̏ꍇ�A����I�Ȑ����ɂ����Ă͌J��Ԃ���Ȃ��悤�Ȉ�̏o�����Ȃǂ������邾�낤�B����������I�����ɂ����Ă��A�������͈��ʐ������Ƃɗl�X�Ȑ��_���s���Ă���B�����̈��ʊW�́A�q���[���̌����u�K�R���v�����o�����Ƃ��ł��Ȃ����A������Ƃ����Ĕے���ł��Ȃ��̂ł���B�߂��������ߋ��̏o�����A�Č��ł��Ȃ��o�����ɂ�������ʐ�������Ɍ����邱�Ƃ����ł��Ȃ��B�i���Ɂu�����I���ʊW�v�̂܂܂Ȃ̂ł���B
�i�S�j�u���R�v���Ƃ������߂͂����Ȃ�ꍇ�ɗ^������̂��낤���H
��ʓI�ɁA�u�w�Z�̑�������̎��R�v�Ƃ��u��Ђ̑�������̎��R�v�Ƃ��A�u���R�v�Ƃ͂����܂ł������������ɗp������T�O�ł���B��m�����̋c�_�̒��ł́u���ʗ�����̎��R�v�ł��낤�B
�����A����܂ł̋c�_����A�u���ʗ��Ɏx�z����Ȃ��v�Ɗ��S�Ɍ�����Ȃ����Ƃ����������Ǝv���B���l�Ɂu���ʗ��Ɏx�z����Ă���v�Ɗ��S�Ɍ����邱�Ƃ��ł��Ȃ��̂ł���B
������Ȃ����Ƃ́u������Ȃ��v�ƌ��������Ȃ��̂ł���B
�����A���Ɂu���ʗ��Ɏx�z����Ȃ��v�ƌ����ꂽ�Ƃ���ŁA���ꂪ�u���R�v�ł���Ǝ��������̂ł��낤���H
���ɏq�ׂ����A�o���͂�����������ė�����́A���ꂪ�K�R�����R���͊W�Ȃ��ɂ�������ė�����̂ł���B���c�͎��̂悤�ɏq�ׂĂ���B
�@�܂���X�͕��ʂɈӎu�͎��R�ł���Ƃ����ċ���B�����������鎩�R�Ƃ͔@���Ȃ邱�Ƃ������̂ł��낤���B������X�̗~���͉�X�ɗ^����ꂽ�҂ł����āA���R�ɂ�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B��������^����ꂽ�Ő[�̓��@�ɏ]���œ��������ɂ́A���Ȃ��\���ł����Ď��R�ł������Ɗ�������̂ł���A����ɔ����A�����铮�@�ɔ����ē��������͋�����������̂ł���A���ꂪ���R�̐^�Ӌ`�ł���B�i���c�����Y�w�P�̌����x��g�V���A48�`49�y�[�W�j
�E�E�E�v����ɓ��@�Ɠ��@�A�ӎu�ƈӎu�Ƃ̌��ˍ����A�������ɉ����Ċ������I���o�ɂ����́A�Ƃ��������ł���B���@��ӎu���̂��̂���t���̉��߂ł͂��邪�A������ɂ���A���_�I���������g������a�����A������������I���o���u���R�v�Ƃ������̂̎x���ɂȂ��Ă���ƌ����Ȃ����Ȃ��B
���́u���R�v�Ƃ͏�\�킷���́A�Əq�ׂ����Ƃ����邪�A��L�̈Ӗ��ł͏�I���o���v�f�Ɋ܂߂�K�v�����邩������Ȃ��B�����A����Ȃ�u���R�v�Ƃ͉����A�Ƃ������Ƃɂ��Ă������������ɒ�`����K�v������Ǝv����B�u���R�v�̈Ӗ��ӓI�Ɋg��E�k�����Ă��܂��A���_�������悤�ɂ������邩��ł���B
�����A���ƂȂ�̂́A��ɏq�ׂ��u�w�Z�̑�������̎��R�v�Ƃ��u��Ђ̑�������̎��R�v�ɂ���A���ǂ̂Ƃ���͖ړI�Ƃ��̑j�Q�v���Ƃ̊Ԃ́u�����v����т���ɔ������炩�̊���E��I���o�Ɏ�����̂ł͂Ȃ��낤���B
���̂悤�ȁu�����v�������炷�̂��s���R�A�����炳�Ȃ��̂����R�A�Ƃ����������������Ƃ��\�ł͂��낤�B
�i2017.11.26[��]�j
|