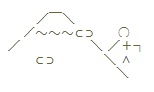思想的、疫学的、医療について
http://syuichiao.hatenadiary.com/
というブログの
時間は実在しない?マクタガートの「時間の非実在性」を読んでみた。
http://syuichiao.hatenadiary.com/entry/2017/02/14/180000
・・・という記事でマクタガートについて説明されていた。
マクタガートは時間に関してA系列とB系列、さらにC系列という概念を導入したのだそうだ。
A系列・・・遠い過去から近い過去を経て、現在へと、そして現在から近い未来を経て遠いい未来へと連なる一系列
B系列・・・より前からより後へと連なる一系列
C系列・・・出来事の順序(時間的なものではない)
変化と時間が入ってきて初めてC系列はB系列になる。
時間的でないC系列は順序はあっても方向性はない。
A、B、C系列を整理すれば、A系列+C系列→B系列と表せるように思われる。入不二基義氏によるマクタガート解釈、すなわちA系列C系列=B系列とするのは端的すぎるという批判もある。
・・・「出来事の順序(時間的なものではない)」に目を付けたのは良いとして、「変化と時間が入ってきて」C系列がB系列になる、という見解はひっくりかえっていないか?
そうではない。経験(出来事でも良いが)の変化がまずあって、それを時間の流れと呼んでいる、ということなのである。
今はまだ復旧していないが、かつて分析した以下の泉谷氏の論文においてもマクタガートについて触れられている。
泉谷洋平著「行為の自己言及性と時空―人文地理学者のアンソニー・ギデンズ理解をめぐって―」『空間・社会・地理思想』 7号 2-16頁, 2002年
マクタガート(McTaggart 1988)は,「変化」が時間の本質であるという。変化を認知することは, 未来であったところのものが現在になり,それがさらに過去になることを認識することである。そして,このような変化を本質とする時間は,経験的なレベルでは実在しない。この論証の帰結は意外な印象を与え,多くの反論がなされたが,およそ考え付く反論はダメット(1986: 370-381)によってことごとく論破されており,マクタガートの提示した論証は正当であることが認められている(大澤1994: 313, 1999: 140-150)。そうであれば,われわれは,何らかの出来事が「非時間的な関係に立っているのに,それをわれわれが時間的だと誤解するのだ」(ダメット1986: 380)と考えざるをえない。そして,まさに実在しない時間が現実として体験されるところに,Ⅱ(1)で確認したパラドクスが巧妙に隠蔽されるのである。(泉谷氏、6ページ)
・・・”「変化」が時間の本質である”という見解は良いのだが、”変化を本質とする時間は,経験的なレベルでは実在しない”というのは微妙である。「変化」は経験しているが「時間」は経験していない、と言った方がより正確か。
”何らかの出来事が「非時間的な関係に立っているのに,それをわれわれが時間的だと誤解するのだ”というのもなかなかに鋭い指摘ではあるのだが・・・そこからなぜ、”実在しない時間が現実として体験される”ことになるのか。「経験的なレベルでは実在しない」のである。要するに”体験されていない”ということなのである。ここの齟齬を泉谷氏はどのように考えておられるのだろうか?
泉谷氏の「変化」に関する見解も転倒したものである。
ある状態Aがある状態Bへ変化するということは, 当然,AとBとの間に何らかの意味で差異があることを意味する。しかし,AとBが単に異なるのであれば,われわれはそれを変化とは呼ばない。たとえば,「信号が赤から青に変わった」という言葉が意味 を持つのは,赤から青に変わった何ものかが,何も のか(信号)としての同一性を保持しているからである。これに対し,赤い箱と青い箱が並んでいる時に,両者の差異について「赤が青に変わった」というように言及することは,通常意味をなさない。このように同一性が想定されない,同一性をそもそも想定していないようなケースにおいては,「赤が青に変わった」という言明は無意味であり,変化について語ったことにはならない。つまり,ある状況を「変化」と呼びうるためには,二つの事象の間に差異がありながら, なおかつ同一性もが保持されていなければならないのである。(泉谷氏、6ページ)
・・・こういった見解の問題点は、
哲学的時間論における二つの誤謬、および「自己出産モデル」 の意義
http://miya.aki.gs/miya/miya_report17.pdf
・・・で既に述べた。泉谷氏の言われる「規則のパラドクス」ついても、このレポートで(間接的にではあるが)それが詭弁であることを説明している。要するに単なる「経験則」をアプリオリと取り違えているのである。
未来・過去・現在の「三兄弟」からなる「時間」である。「三番目[現在]がいられるのは,一番 目[未来]が二番目[過去]に変身してくれるため」というのは,時間の本質が「変化」にあるとする, ここでの解釈に符合している。「ほんとはまるでちがうきょうだいなのに,…それぞれたがいにうりふたつ」とは,もちろん,未来・過去・現在のそれぞれが排他的でありながら同一性を保持していることを示している。(泉谷氏、7ページ)
・・・上記、泉谷氏の説明するエンデの見解も、同様な誤謬に陥っている。
また、ギデンスはハイデガーを援用して、次のように述べている。
ハイデガーにおいては、現前―それは無から存在が生じるような「現前化(presencing)」として理解される―が、「今(nows)」の無限性としての「現在(present)」に取って代わる。時空間は、もはや、「計算された時間における二つの今‐点(now-points)の隔たりを意味しない。それは「到来(futural approach)〔と過去の現在〕が相互に届け合うようにして開かれ空いたところを名指したものである」(Giddens 1983:78)。(泉谷氏、10ページ)
・・・”過去や未来が現在とともにあるという意味での「同時性」”(泉谷氏、11ページ)とも言えるようだ。
ギデンスがその根拠とする「規則」の「先験性」とは、実のところ、これまでの経験の積み重ねにより導かれた「経験則」がこれからの経験においても適用されるであろう、という推論への確信にすぎない、ということである。
ギデンス、泉谷氏は、「規則」を伴う「論理」がいかなるものか、「論理」とは何なのか、そこに全く無頓着なのである。あたかもそれが「先験的」に与えられるものであるかのように錯覚しているだけなのである。
いずれにせよ、上記のギデンス(ハイデガー?)の見解は、「過去」「現在」「未来」という客観的時間概念を全くエポケーできないまま、その概念を根拠の薄弱な論理によって組み合わせたものであるにすぎないのだ。何度も繰り返すが、「過去そのもの」「現在そのもの」「未来そのもの」はどこを探しても見つかることはない。どこにもないものが届け合ったりともにあったりしようがない。それらはただの概念(言葉)のいじくりまわしに他ならないのである。
**********************
入不二基義著「現実の現実性と時間の動性」『哲学論叢 』(2017), 44: 1-15
を少しだけ読んでみて気が遠くなった・・・が、一応最後までざっと読んでみた・・・。上記のような誤謬を放置したまま、いたずらに概念どうしの辻褄合わせをしているだけのように感じられる。
とにかく、私が「哲学的時間論における二つの誤謬、および「自己出産モデル」 の意義」で示した二つの誤謬を乗り越えないことには、時間に関する哲学的問題は解決することはないのだ。
実際、永井は<私>や<今>と「これ(この)」をほぼ互換的に使っていて、どれも「中心指向性(収斂性)」とでも呼ぶべき力の向きを共有している。また、第0次内包(私秘性)を指示する「これ(この)」もまた、同様の「中心指向性(収斂性)」という力の向きは共有している。「中心指向性(収斂性)」は、ウィトゲンシュタイン(『哲学探究』253)に倣って言えば、「これ(この)」を強調して言いつつ自分の胸の辺りを叩くジェスチャーによって象徴されるだろう。(入不二氏、2ページ)
・・・純粋経験の主客未分とは、(西田の見解とは別に)ウィトゲンシュタイン自身が言っているように、「形而上学的な主体」はない、ということに尽きる。具体的経験として「形而上学的主体」など実際に現れてはいない、という事実なのである。
それは「自分の胸の辺りを叩」いた場合においてもそうなのである。そこには体を動かした際の体感感覚と(触感含む)、「これ」と言ったのであればその言った言葉と、それだけなのであって、「中心指向性そのもの」の経験などどこにも現れてなどいないのである。
それらは、経験と経験とを繋げ、その関係を説明するための「仮説概念」以上のものではない。
「観念的・形而上学的」な私の経験などどこにもないし、「今」という経験などどこにもない。経験しているのは「今」ではないのだ。
入不二氏は、次のような区分をされている。(入不二氏、4ページ)
(1)「私の現実・現在の現実・世界の現実」:有内包
(2)「現実の私・現実の現在・現実の世界」:脱内包
(3)「現実の現実性」それ自体:無内包
・・・このような区分をすること自体が間違いというわけではないのだが・・・問題は(3)である。
(3)は、人称・時制・様相の表現を消し去ることで、偏在一様な現実を表現しようとしている。結局、(3)によって表現される「現実性それ自体」「無内包の現実」は、無人称・無時制・無様相でもあるということである。「無内包の現実」は、どんな領域への囲い込みや中心化もすべて無効にしてしまう「偏在的な現実」なのである。(入不二氏、5ページ)
・・・「現実」が「偏在的」とかわけわからないが、ここまでの説明においてはまぁそれはそうかなぁ、という感想である。しかし、
「現実」が「現前」「顕在」と取り違えられやすいという点にあるだろう。「現に」という現実性は、ありありと現前しているかどうか、顕在的であるか潜在的であるかとは別のことである。現実はたとえありありと現前していなくとも現実であるし、たとえ潜在的であるとしても、「現に」潜在しているのだから現実に他ならない。現実は、現前と同一ではないし、潜在とも対立しない。(入不二氏、5ページ)
・・・となると台無しである。これでは(1)との混同になってしまう。私が見て居なくても「現実」が存在するというのは、経験の因果的把握に基づく客観世界認識以外の何物でもない。
このあたりも、「哲学的時間論における二つの誤謬、および「自己出産モデル」 の意義」の第二章で説明している。
実際の具体的経験、見えているもの・聞こえているもの・感じているもの、それは否定しようのない「現実性」というか「事実性」としての明証性を有するものである。もちろん言葉(を喋ったり聞いたり読んだり)もそうである。
現実性を、具体的経験から切り離して考えれば、それは既に「仮想世界」の構築、根拠のない架空論理の辻褄合わせとなってしまう。
「現実」であることと「現在」であることとは別のことである。にもかかわらず、(過去や未来ではなく)現在を「ありありと現れている何か」として、特権的な現実であるかのようにみなしてしまうと、現実は現在へと不当に狭まり、現実性は現前性・顕在性に変質してしまう。(入不二氏、5ページ)
・・・このあたり、惜しい見解である。入不二氏は、「現実」と「現在」とは別のことだ、と気づいておられるにもかかわらず、「現前性」と「現在」とを混同してしまっているのだ。「現前」という表現が誤解を生んでしまうのかもしれない。厳密には「現前」というよりも、単に「現れている経験」なのだから。
入不二氏が指摘すべきなのは、「ありありと現れている何か」は「現在そのもの」の経験ではない、ということなのである。それだけで良いのだ。「現実」として「ありありと何かが現れている」のである。ただそれだけのことだ。
そうであれば、(永井氏の言われるように)「現在(今)が端的な現実性」を持つ」(入不二氏、9ページ)かどうかという問題など、お話にならないと一蹴すれば良いだけである。
「デジタルな点滅反復」(入不二氏、10ページ)も問題外である。入不二氏ご自身もこの理論が決定的解決になるとは思われていないであろう。
「時間の経過」は、他の変化(状態変化や位置移動など)の背景として潜在するのみであって、けっして前景化することはない。そこで時間変化は、他の変化(時間変化ではないふつうの変化)に寄生することによってしか、表象することができない。その点では、時間変化は他の変化に依存する。時間の経過が、川の流れや時計の針の移動などの変化、あるいはものの状態変化などに重ねられて表象されるのは、このためであり、その表象的な依存関係は必然でもある。
にもかかわらず、それ自体は表象され得ない時間変化が背後で潜在進行していてこそ、その他の変化が前景で進行できる(とみなされねばならない)。また、たとえその他の変化が起こらなかったとしても、時間変化のほうは表象されないだけで潜在進行している(とみなされねばならない)。その点では、時間変化は、他の変化に依存しない絶対的な変化なのである。(入不二氏、10~11ページ)
・・・このあたりの見解も惜しいところではある。入不二氏は経験を素直に受け取れば良いだけなのである。「時間が前景化することはない」とはどういうことか・・・それは経験として現れることがない、ということなのである。
そして、時間というものが、夜明けとか日没とか、星や月の動きとか、水晶振動子の周期であるとか、そういう具体的な物の動きで定義づけられていることも事実なのである。つまり、
経験の変化が時間の変化と見なされている、ということであって、
時間の変化が”潜在進行”しているから経験の変化が生じるのではない、
ということなのだ。「時間変化が潜在進行している」という見解はまさに、入不二氏が使われている「有内包の水準」の認識に外ならない、ということなのである。
(2018.3.28[水])
|